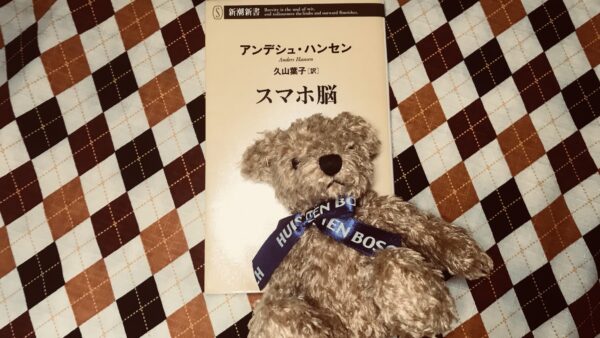樺沢先生の本を久しぶりに読んでみましたよ。
本書の構成
本書の特徴は、なんといってもⅡ部構成になっているところ。
第1部 イラストでわかる 最高の1日をつくる行動の最適化
第2部 最新科学・研究結果で説明する 最高の1日をつくる行動の最適化
「最高の1日をつくる行動の最適化」を、イラストでわかりやすく(第1部)
より詳しく学びたい人には科学や研究結果をもとにした説明(第2部)も、
と2段階設定になっています。
普段本を読まない人は、ひとまずイラストだけをパラパラ眺めてみてもOK。
第2部も、ひとつひとつのセンテンスは短くわかりやすく区切られているので、気になるところだけつまみ読みしてもOK。
(個人的に、第I部のイラスト版はもう少し色味が落ち着いていると良かったなあ。蛍光オレンジでちょっと目にチカチカします。個人的感想です)
*
これまで他の著作でも書かれていたことの繰り返しも多いです。
でも「それ前も読んだよ」という内容でも、意外と日々の生活に実践できていないこともあったり、意外とのそのなかに再発見や新発見もあったりします。
これまで樺沢先生の本を読んだことのない人にももちろんおすすめ。
日々をちょっと工夫して、健康に生き生きとパフォーマンスを上げて豊かに生きたい人に。
うつ病になる前の、予防的な意味を込めて、など。
参考にできるところを、まずはひとつふたつと取り入れていけると良いかなと思います。
感想
今回も、わたし目線で気になったところを3つピックアップしていきます。
<お品書き>
- 「休憩」の最適化
- 「やる気」の最適化
- 「マイペース」=「マイベストペース」
よかったらお付き合いくださいませ。
「休憩」の最適化
みのりさんはたぶんHSP気質で、(デフォルトで)いろんなところに神経張りめぐらせていっこいっこめちゃくちゃ考え込んでしまうので、たぶん人より(脳が)疲れやすい。
その割に、休憩が下手なので、「休む」ことは常に人生の重要課題です。
休憩時間は、脳を興奮させるのではなく、休ませなければいけません。
(P156 Ⅱ部 第2章「昼」の最適化)
多くの人は、仕事時間中、パソコンに向かって、膨大な視覚情報を処理しているので、せめて休憩時間くらいは視覚情報から脳を解放するべきです。
(P157 Ⅱ部 第2章「昼」の最適化)
休憩時間にスマホをするのは脳にとってあんまり休みになってないよーという話。
これ、前もどこかで読んだことがあります……
アンデシュ・ハンセンの「スマホ脳」という本です。
▷▷ この本の感想はこちら
ついついスマホを触ってしまいますよね。
あと、デスクワーク(座っていること)が多い人は、休憩を兼ねて立ち上がって歩くなどの軽い運動を取り入れたほうが良いそうです。(要は座りっぱなしは良くないということ)
アメリカのベイラー大学で行われた休憩頻度の研究によると、「頻繁に休憩をとれば、休憩時間は短くても効果がある」「休憩の回数が少ないと、1回の休憩に長い時間をかけなければ、回復効果が得られない」「午後よりも朝の休憩の方が効果が高い」ということがわかりました。
(P159 Ⅱ部 第2章「昼」の最適化)
総括すると、疲れすぎる前にこまめに休む。
(P160 Ⅱ部 第2章「昼」の最適化)
こまめに休憩が良いそうです。メモメモ。
*
あと、夜寝る前の時間の過ごし方も。
1日24時間、あわただしく過ごしているので、せめて寝る前「30分」だけは、リラックスして、のんびり過ごしてみませんか。
それが、睡眠を深め、疲労を回復し、明日の活力につながり、翌日のパフォーマンスを高めるのですから、非常に有益な時間投資といえます。(P199 Ⅱ部 第3章 「夜」の最適化)
理想を言えば、寝る2〜3時間くらい前からリラックスモードにできるほうが良いのでしょう。
でも現実はなかなかむずかしい。
できる範囲で「寝る前はリラックスモード」とできると良いのかなと思いました。
「やる気」の最適化
最後は、「やろうと思っているんだけど、なかなか取り掛かれない」「やる気スイッチはどこにあるんだろう」とお困りの方にこちら。(なんかの宣伝のようだ・笑
「やる気」が出ないと仕事も勉強もはじめられないという人は、どうすればよいのでしょうか。
その答えは、「さっさとはじめる」ことです。
(中略)「やる気が湧かないときは、とりあえずはじめる」というのが、脳科学的に正しい方法なのです。(P211 Ⅱ部 第4章 「仕事」の最適化)
以前読んだフォッグ先生の「習慣超大全」(タイニー・ハビット(小さな習慣)を推奨)の本にも似たようなことが書いてありました。
▷▷ この本の感想はこちら
とりあえずやってみるときに、そのための第一歩のハードルを小さく(低く)していくこと。
わたしも最近スモールステップで「とりあえずやってみる」をちょっとずつ実践するようにしています。
まあそれでも乗らないときもやっぱりあります、あります。
そういうときは「いまは身体が休めと言っているのかなあ」と思うようにしています(笑
(休むときについついスマホを触ってしまうことが悩みではあります…)
「マイペース」=「マイベストペース」
私は、「やれる範囲でやっていく」という言葉が大好きです。
なぜならば、結局のところ、やれる範囲でやっていくしかないのです。自分の能力や許容範囲を超えて仕事をしたり、頑張ったりしすぎると短期間ではなんとかなるものの、長期になれば身体か、メンタルのどちらかを壊す羽目になるでしょう。(P318〜319 Ⅱ部 第8章 「人生」の最適化)
やれる範囲でやっていくことは、「マイペース」と言い換えることができます。また「マイペース」=「あなたにとってベストのペース」です。(マーカー)
(中略)人生という長距離レースでは、「無理する人」「頑張りすぎる人」は全て脱落します。
マイペースで走り続ける人が、より遠くまで走ることができ、いつの間にか先頭集団に入っているのです。
無理することなく、自分の速度で歩みましょう。(P319 Ⅱ部 第8章 「人生」の最適化)
とても励まされる言葉だなあと思いました。
自分にとってちょうど良いペースが、ベストなペースであること。
一見当たり前のことなのですが、意外と盲点だったなと思います。
周りの人と比べて焦って頑張り過ぎて、無理がたたって心身の調子を崩していては元も子もありません。
自分の体感、感じ方はとても大切です。
(中略)
結局のところ、「楽しい」「快適」「気分がいい」というものでなければ、継続し、習慣化することは不可能です。
何度か試してみて「これはよさそうだ」という感覚があれば、自然と継続できるでしょう。
「自分の感覚」をもっと信じてください。
「自分の感覚」を研ぎ澄ましてください。あなたに合っているものは、あなたの感覚が一番、教えてくれるはずです。
(P318 Ⅱ部 第8章 「人生」の最適化)
自分の感覚を研ぎ澄ませていくこと。簡単なようでむずかしい。
でも自分に合っていることは、自分(の感覚)がいちばんわかっているのだろうなと思います。
どんなときに自分はちょうど良いペースを保てるだろう。
自分が心地よい、楽しい、こころが弾むのはどんなときだろう。
逆に調子を崩すときは?
きっとその人によって違うはずです。
自分の感覚を大事にして、マイベストペースを見出していけると良いなと思いました。
関連情報
▽ 関連の本、記事
正式名称は『スタンフォード行動デザイン研究所の自分を変える方法 習慣超大全』です(長い)。 「よくある習慣の本?」と思い…
*